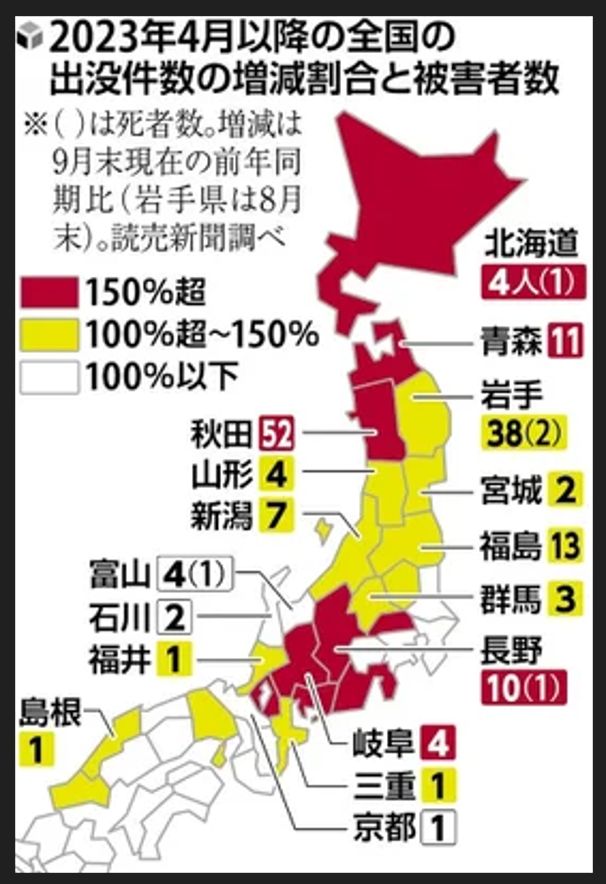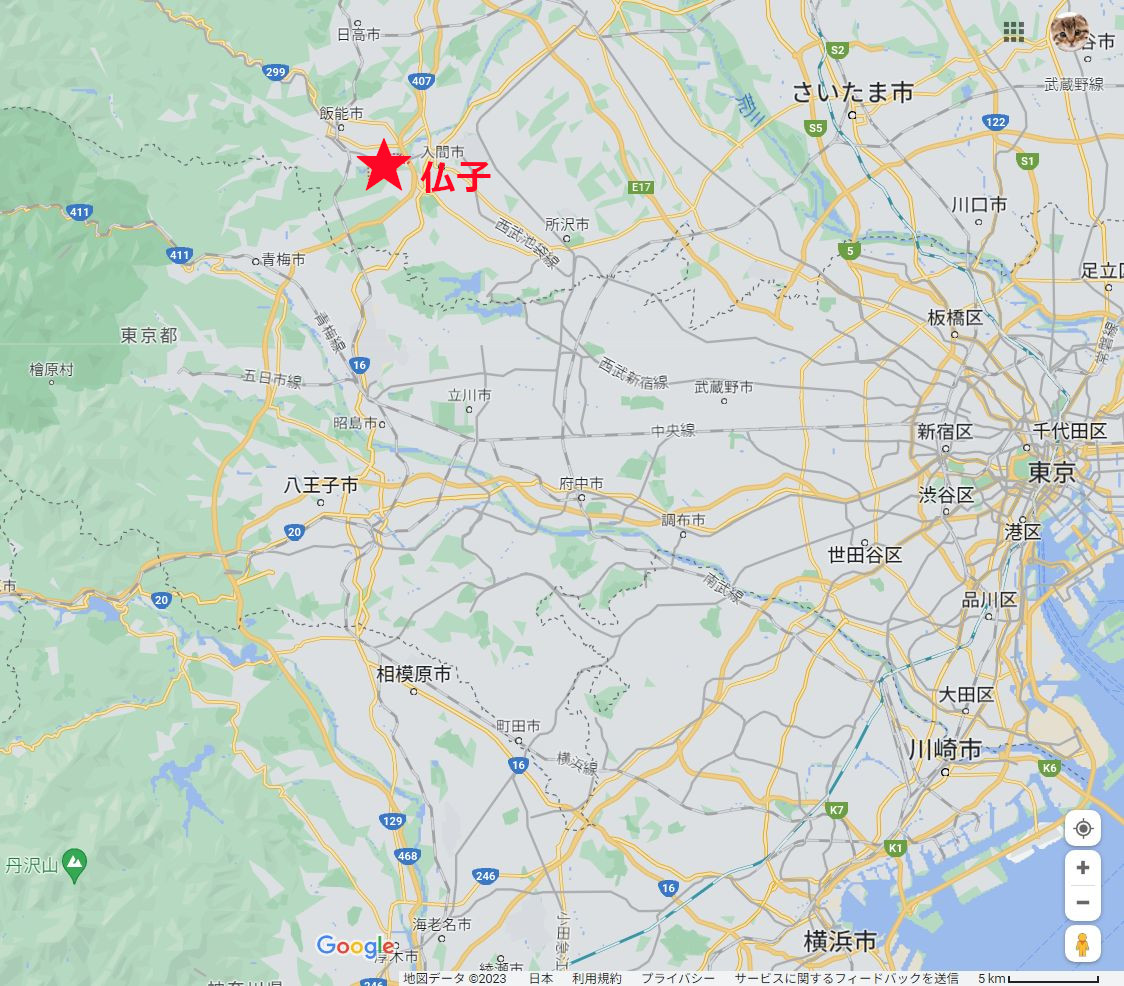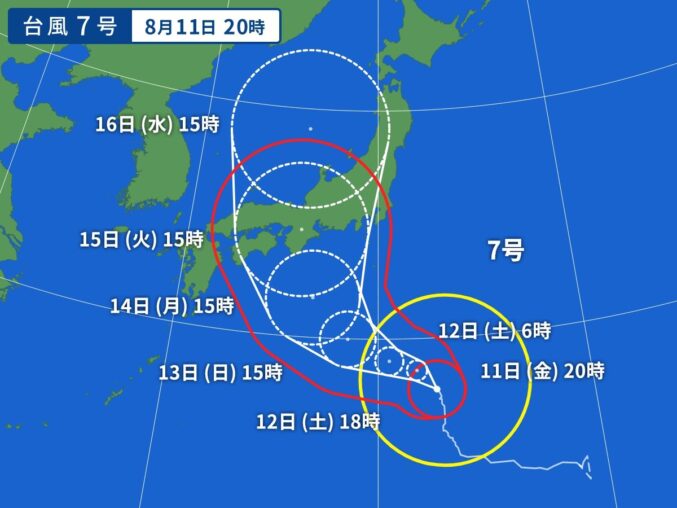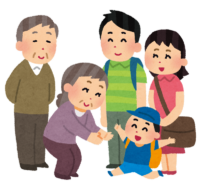山崎クリスマスケーキのCMが流れると、「年末だなぁ」という気分になります
山崎ではなく、デパートの高島屋が販売したクリスマスケーキが「激しく崩れて」届いたということで話題になっています
配送中に崩れないように「冷凍」して配送しているそうなので、製造ラインの冷凍前後の工程に問題があったのか?
あるいは冷凍されたケーキを崩すくらい超荒っぽい配送だったのか?

▲激しく崩れて届いた、高島屋のクリスマスケーキ
少しぐらい崩れていても味は一緒で、食べればおなかの中でぐちゃぐちゃに崩れちゃうんだからいいじゃん
などと大らかな人は、世界一品質に厳しい日本の顧客には少ないでしょうね
製造ラインが原因なら山崎の社内組織でしょうから、該当工程の責任者は、もう正月どころじゃなくなりそう
配送に原因があるなら、その配送業者は山崎との契約を切られるでしょうから、これはこれで寒いお正月を迎えることになりそうです
物流業界の労働環境が厳しいことが問題になり、来年から新しい残業規制が始まって、産業界では物流危機の可能性が指摘されています

ネット通販では「送料無料」が多く、その無理なコストダウンのしわ寄せが物流業者に及び、現場担当者のストレスが限界に来ています
海外では、配送品を床にたたきつけたりして荒っぽく扱う配送担当者もいて、それが当たり前になっている国も少なくないようです
(^_^;)
* * * * * * * * * *
12/24、高島屋オンラインストアで販売した一部のクリスマスケーキが激しく崩れた状態で顧客に届いた。
「原形がないくらいに崩れていて……。
ひどすぎて笑ってしまいました」
女性顧客(48)はそう話す。
高島屋は取材に、崩れた原因は調査中としている。
12/24午後1時現在、苦情が約220件寄せられている。
▲中国の配送業者 荷物を乱暴に扱っている